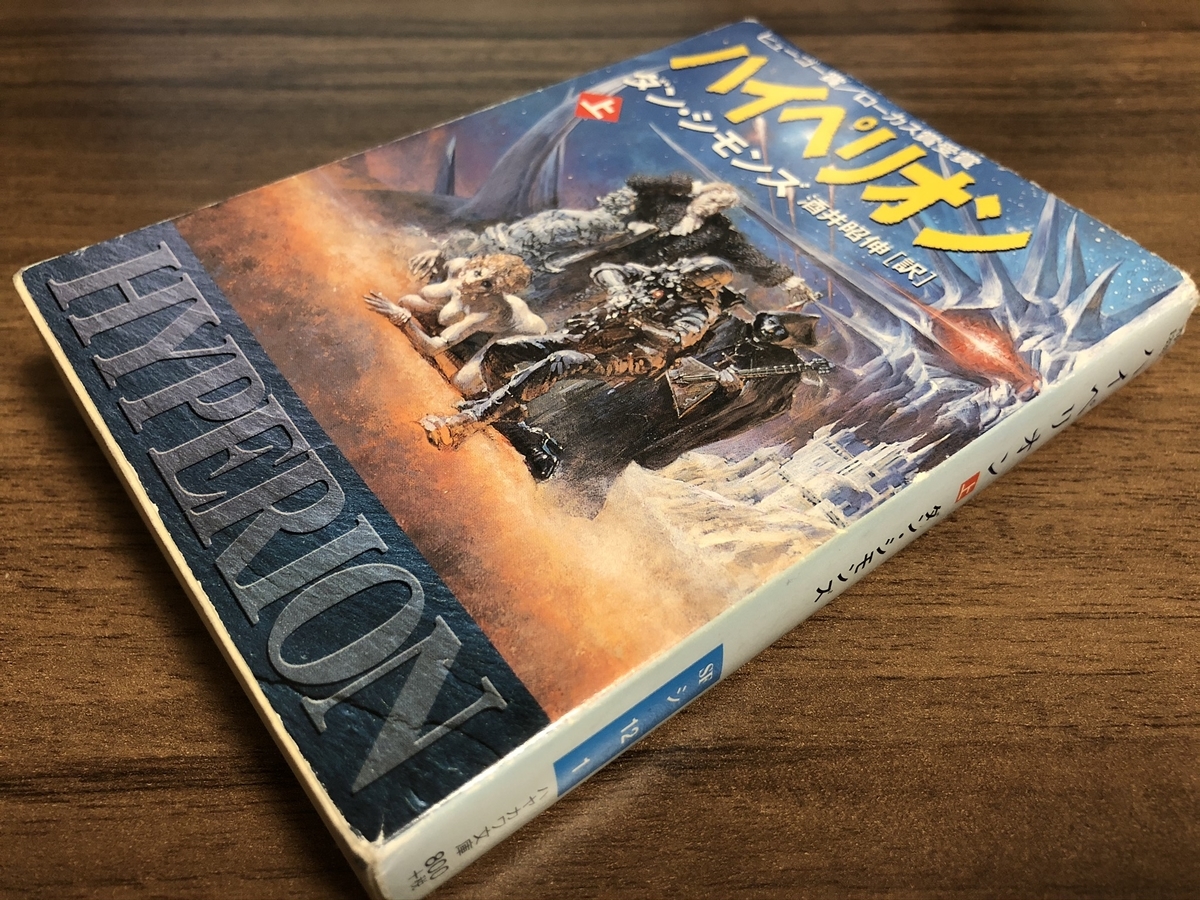ハイペリオンの六つの物語のうち、最後の物語である、領事の物語について紹介、解説します。領事の物語は、一番読みにくい物語かもしれません。それでいて、最後の物語にふさわしい伏線回収の要素を多く持っています。といっても、物語は『ハイペリオン』から『ハイペリオンの没落』へ移っていくので、全体の物語としては、まだ半分です。
前回の物語はこちら。
解説(はじめに)
領事の物語は少し難解なので、解説から入ります。まず、登場人物から整理します。マーリン・アスピックは連邦の若きシップマンで、マウイ・コヴェナントに転位ゲートを建設する事業に従事していました。シリはマウイ・コヴェナントの先住民の少女で、初期の播種船でマウイ・コヴェナントにたどり着いた開拓民の末裔です。二人には、アーロンとドネルという息子がおり、領事はドネルの息子、つまりマーリンとシリの孫にあたります。
シリとマーリンが7度にわたって逢瀬を重ねた記録が、領事によって語られるのですが、その時系列がばらばらで断続的なので、領事の物語は一見してその内容を把握しづらい面があります。また、マーリンにとっては5年間の物語でありながら、シリにとっては65年間の物語であることが、非現実的な飲み込みづらさを生んでいます。
マーリンは超光速でマウイ・コヴェナントと連邦を往復しているため、その往復期間はマーリンにとって9か月、シリにとって11年になります。マーリンが一年弱の航行を終えたとき、シリは11歳も歳をとっているのです。その二人に許された逢瀬の時間はたったの7回。しかも最後の7回目には既にシリは他界していました。二人がともに過ごした期間は一年にも満たないわずかな時間でしたが、二人は愛し合い、子供も設けました。時空の隔たりがあるからこそ、シリとマーリンの最初の出会いは現地で伝説となりました。そんな奇蹟的なロマンスが、領事の物語の根底にあります。そして、彼らとマウイ・コヴェナントが辿った歴史が、領事の行動原理を形成しています。
時系列を整理すると次のようになります。
| マーリン | シリ | アーロン | ドネル | 領事 | 出来事 | 主なページ(文庫本) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19歳 | 15歳 | ― | ― | ― | マイクの死。その事件が後に伝説になる。 | P352~断続的に |
| 20歳 | 26歳 | 0歳 | ― | ― | シリがアーロンを身ごもる。多島海のイルカの描写。 | P373 |
| 21歳 | 37歳 | 10歳 | 0歳 | ― | シリがドネルを身ごもる。 | P361 |
| 21歳 | 48歳 | 21歳 | 10歳 | ― | アーロンが独立主義者として惑星警察に抵抗し殺害される | P414 |
| 22歳 | 59歳 | ― | 21歳 | ― | 年齢差のある官能の描写。 | P355 |
| 23歳 | 70歳 | ― | 32歳 | ― | 転位ゲート開通後の会話。 | P395 |
| 24歳 | ― | ― | 43歳 | 9歳 | シリは既に死亡。転位ゲートの開通と崩壊。シリの反乱の勃発。 | P346~断続的に |
※年齢は目安です。
シリの物語に切なさを感じるのは、実はごく身近にある出来事に似ているからです。例えば、70歳の母と35歳の息子という関係性を設定してみましょう。シリとマーリンのように航時差で隔てられてはいないとはいえ、一年に一度会うような間柄であれば、似たようなことが起こります。老齢の母の一年と、まだまだ青年と言ってもよい息子の一年には、かなりの違いがあります。個人差にもよりますが、正月やお盆に帰省して、半年ぶりに会った父と母が老け込んだなと思った経験を持つ人は多いと思います。この切なさは、若い人にはきっと分かりません。事実、私が『ハイペリオン』を初めて読んだ大学生の時、シリとマーリンの物語の切なさは頭では理解できても、心で感じることは出来ませんでした。しかし、歳を重ねてから読んでみるとこれはいけない。涙が出てくるのです。思えば、シリとマーリンは初めは恋人関係でありますが、シリの加齢とともに母と子の親子関係としても捉えることができるような気がします。
領事の物語:思い出のシリ(あらすじ)
巡礼者である領事は、古いコムログを取り出して、その記録を語りだした。その内容は、今ではシリの反乱と呼ばれる(そして、無残にも失敗に終わった)マウイ・コヴェナントの独立戦争の、前日譚ともいうべきものであった。
シリとマーリンが出会ったのは、シリの反乱が勃発する65年前のことだ。もっとも、マーリンにとっては、5年前の出来事でしかないのだが。転位ゲート開設の乗組員として、連邦とマウイ・コヴェナントを往復するマーリンには、シリとの逢瀬は時間的にあまりにも限られていた。シリとマーリンを隔てた航時差が生み出す現実は残酷で切ないものだった。
シリは政治家として立身した。彼女のイデオロギーは一貫して独立主義者に与するものではなかった。しかし、後にシリの反乱と呼ばれるように、独立運動の精神的主柱となった背景には、シリとマーリンの息子であるアーロンが独立主義者に紛れて殺害されたことが大きい。そして、マウイ・コヴェナントが転位ゲートで連邦と繋がれば、マウイ・コヴェナントは連邦の政治と経済の食い物にされ、いままでのマウイ・コヴェナントではいられないことも。最初の転位ゲートが開通したとき、シリはすでに他界していたが、計画されていた反乱は実行された。転位ゲートは開通と同時に破壊され、マウイ・コヴェナントは一瞬の後に再び11年の時空によって隔絶された。
連邦の FORCE 艦隊が現れるまでの5年の間に、反乱軍は艦隊を急造したが、それらは FORCE によってあっけなく蹴散らされた。マウイ・コヴェナントはやがて停戦し、そして正式に連邦に加盟した。マーリンは多島海の戦いで戦死したとされる。シリの一族、つまり領事の一族は、その多くが反乱に殉じた。ただ、シリの息子であり領事の父であるドネルは、連邦の上院議員となり、マウイ・コヴェナントの初代惑星知事となった。領事はそのもとで外交官としてのキャリアを歩み始める。
マウイ・コヴェナントがそうであったように、連邦は開拓星の、先住民、先住文化、先住性物を尊重しなかった。連邦がかつて知的生物に遭遇しなかったのは偶然ではない。開拓星が転位ゲートによって連邦と繋がる前に、知的と評価される種は駆逐されてしまうからだ。領事は外交官として開拓星に赴任し、連邦の暗部で手を汚し続けてきた。ファール、ガーデン、ヘブロンと転任を続けるうちに、ついに領事は精神を病んだ。
全く知られていないことだが、<テクノコア>は実戦部隊を持ちアウスターを執拗に攻撃していた。そして、アウスターと FORCE 双方の実力を試すために、ブレシア人を焚きつけて、アウスターを攻撃させた。かのブレシアの戦いは連邦による執拗な挑発に対するアウスターの報復であり、始まるべくして始まったのである。驚くべきことに、この計画は<テクノコア>だけでなく、連邦の上院でさえも加担していたという。結果として、アウスターは大挙してブレシアになだれ込み、<テクノコア>と連邦は目的を果たした。<テクノコア>は双方の実力を分析するに足るデータを得、連邦は厄介な自治政府が壊滅したブレシアで漁夫の利を得ることができた。当時、ブレシアに赴任していた領事は、これにより妻グレシャと息子アーロンを失った。
ブレシアの戦役によって昇進した領事は、アウスターとの交渉役に任じられた。領事に直接話をしたのがグラッドストーンだった。その要点は、アウスターを挑発し、連邦を攻撃させることにあった。対象はハイペリオンだ。ハイペリオンがアウスターに攻撃されれば、連邦はハイペリオンを強制的に併合せざるを得ない。<時間の墓標>は未来から遡ってきた存在ゆえに、誰に利するものか分からない。<テクノコア>はそのため、頑なにハイペリオンの併合に反対してきた。ハイペリオンを併合すれば、<テクノコア>の穏健派が勢力を拡大させることは確実とみられた。
自ら進んでその任についた領事は、個人用の宇宙船が与えられ、外宇宙を放浪し、ついにアウスターと接触を持つに至った。アウスターは<ウェブ>の人間がこの千年間に成し得なかったことを成し遂げていた。アウスターの船団での生活を領事はそう表現する。領事はアウスターに全てを打ち明けた。そして、アウスターもいろいろな情報を領事に与えた。そのひとつは<大いなる過ち>についてであった。<大いなる過ち>は決して過ちなどではなかった。オールドアースの破壊は、人類を宇宙へ旅立たせるために、<テクノコア>と連邦が手を組み、意図的になされたものであった。<テクノコア>の管理下にないアウスターだからこそ、連邦内において<テクノコア>によって巧みに隠蔽されている事実を良く知っていた。
<ウェブ>へと戻った領事は、グラッドストーンに結果を報告した。罠だと知りながらアウスターはハイペリオンを攻撃すること。そして、戦いが始まったとき、二重スパイとしてアウスターに通じるため、ハイペリオンの領事になってほしがっていることを。しかし、アウスターが<時間の墓標>を開く技術を持っていることだけは伏せた。領事はハイペリオンに派遣された。ほどなくして、アウスターのエージェントから連絡が入った。彼らは<時間の墓標>を調査するためにハイペリオンまで来た。アウスターは転位ゲートの技術を持っていなかった。というよりも、転位ゲートの技術は<テクノコア>のみが保守、管理する技術であり、連邦の技術者ですらその原理は明らかでなかった。故に、アウスターはその技術に強く興味を持ったが、結果としてその原理を解明することは出来なかった。しかし、その失敗に至る過程を経て、彼らの時空に対する理解は大きく進歩した。アウスターもまた<時間の墓標>が未来から遡っていることを知っており、遺跡を取り巻く抗エントロピー場を破壊することで、時間の遡行が止まること、つまり<時間の墓標>が開くことを仮定していた。彼らはその仮定を、実験によって確認するために来たのだ。
領事はエージェントを<時間の墓標>へと案内した。アウスターのエージェントは、抗エントロピー場を崩壊させる装置(開放装置)を持っていた、しかし、今はまだ使うときではないとエージェントは言った。アウスターの政治的上層部は、まだハイペリオンへの侵攻を決定していなかったからだ。装置は、侵攻が確定的になって初めて起動される。装置をいったん作動させたら、場の崩壊は止められない。領事は、<時間の墓標>が開いたら戦争に勝利するしか道がないことを念を押して確認したのち、エージェントを射殺した。そして、開放装置を起動した。一見して遺跡に変化はない。一年以上をかけて、場はゆっくりと崩壊していくのである。領事はまずアウスターに連絡をいれた。事故が起きて、エージェントはシュライクに殺害され、開放装置が作動してしまったと。そして、グラッドストーンに連絡を入れ、アウスターの侵攻がほぼ確実であることを告げた。しかし、開放装置のことだけは伝えなかった。
グラッドストーンは領事の労をねぎらい<ウェブ>へ戻そうと言ったが、領事は断ってハイペリオンに近い辺境惑星へ宇宙船を向けた。
解説(続き)
領事の物語は、中に二つの物語を持っています。ひとつは、シリとマーリンの物語である前半部分で、もうひとつは、領事自身の独白である後半部分です。
前半は、学者の物語とはまた別の側面で、胸が締め付けられる物語です。学者の物語はレイチェルが若返っていくという悲劇の物語でしたが、今度はシリが年老いていくという逆の悲劇の物語でもあります。一方で後半は、六つの物語の最後を飾るにふさわしい新事実が明らかになります。前半と、後半のギャップが激しいので、ここもまた理解しづらい理由かもしれません。
プロローグにおいて、グラッドストーンは巡礼者の中にアウスターの内通者がいることを領事に告げました。領事こそがその内通者です。グラッドストーンは領事を連邦のスパイとしてアウスターに送り込んだ張本人ですから、アウスターのスパイがいることを領事に告げるのはどことなく不自然に感じます。グラッドストーンから見れば、アウスターのスパイがいるとしたら、領事はまず最初に疑われる人物だからです。プロローグにおいてグラッドストーンがスパイのことに言及したのには、注意を促すためというよりは、どことなく言動の怪しい領事の心中を察知して、釘を刺したと見るべきかもしれません。
一見して、領事の行動は理解しがたいものがあります。それを理解するために必要なのが、前半のシリとマーリンの物語です。連邦が各惑星を開拓していく構図は、かつてヨーロッパの列強がアメリカ大陸やアフリカ大陸を植民していった構図の相似形です。SFは社会風刺の受け皿とも言われるように、シモンズは過去の風刺されるべき歴史を上手く未来に再利用しました。歴史は繰り返すということです。故郷であるマウイ・コヴェナントが連邦によって蹂躙されていったときから、領事は連邦への復讐を誓いました。多くの一族が戦争に身を投じたのとは違うやり方で、領事は復讐を試みます。そのためなら、ファール、ガーデン、ヘブロンといった開拓星が、マウイ・コヴェナントと同じ道を辿ったとしても、外交官として手を汚すことも厭いませんでした。外交官として出世し、連邦の中枢の一員になったとき、連邦に対して内部から復讐を全うすることができます。領事はその機会をひたすら待ち続けたのです。その間に精神を病み、妻子すら失いました。そして訪れた決定的な機会が、<テクノコア>も巻き込んだ、連邦とアウスターの全面戦争でした。
領事の物語は、得体のしれない存在であったアウスターに、もっとも近づいた物語でもあります。兵士の物語では、アウスターは純粋な連邦の、そして人類の敵でした。しかし、現実はそう単純ではありません。連邦はアウスターを蛮族とすら表現しますが、実のところアウスターは連邦よりも科学面でも文化面でも連邦とは違う独自の進化を遂げた存在です。ブレシアの戦いは、アウスターの一方的な攻撃によって始まったと考えられていましたが、実は<テクノコア>が主導して、連邦が度重なるアウスターへの攻撃を行った結果、報復としてブレシアは攻撃されたのでした。そして、この度、アウスターがなぜハイペリオンを攻撃するのかも明らかになります。<テクノコア>は<時間の墓標>が未知ゆえに、人類が<時間の墓標>に近づくことを警戒しました。アウスターは<テクノコア>とのしがらみを持たないために、積極的に<時間の墓標>へ近づきます。そのアウスターの動きを、連邦は<テクノコア>に対するけん制として、利用しようと画策します。
連邦、アウスター、<テクノコア>の三つ巴の勢力図が浮き彫りになります。巡礼者たちは自らの物語を語り終え、巡礼の旅は<時間の墓標>へ差し掛かります。『ハイペリオン』の物語はここで終了になります。物語は『ハイペリオンの没落』へ続きます。